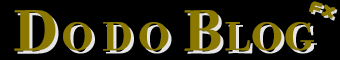こんにちは!どどっちです。
“消防設備士乙7“の試験を独学・一夜漬けで受験したところ、見事に落ちてしまいました!
“乙7は超簡単!”というネットの情報を鵜呑みにして、舐めていました…
また、乙6や危険物乙4は簡単に合格できたこともあって、「乙7も一夜漬けで楽勝に合格できるだろう…」と考えていたことを後悔しています。
非常に悔しいです!
今回のブログでは、同じように乙7に落ちてしまった方や、乙7を舐めている方に向けて、試験の感想や次回の対策について書いていきたいと思います。
消防設備士乙7とは!?
消防設備士乙7は、漏電火災報知器の整備や点検に必要な国家資格です。
「漏電火災報知器」とは、電気の配線や電気機器に関する回線に火災に至るような漏電が発生した際に警報を発し、火災を未然に防ぐ装置を指します。
日本では主にラスモルタル造の対象建築物に設置されており、現代では設置対象となる建築物が減少しているため、需要が少なくなっています。
※ラスモルタル造 … 壁や塗天井用の下地にメタルラスやワイヤーラスなどを使用し、ラスの上にモルタルを塗って仕上げる建築工法。
消防設備士乙7の試験範囲
消防設備士乙7の試験は、筆記試験と実技試験に分かれています。
“実技試験”というのは、実際の設置点検作業を行うわけではなく、鑑別や製図を行う筆記試験のことを指します。
筆記試験
筆記試験の試験科目は、下記のようになっています。
| 基礎的知識 | 電気に関する部分 |
| 消防関係法令 | 各類共通部分、7類に関する部分 |
| 構造・機能 | 電気に関する部分、規格に関する部分 |
乙7の試験は、①漏電火災報知器について・②関係法令・③電気や電気工事の基礎知識の3点が試験範囲です。
実技試験
実技試験の試験科目は、①写真による鑑別問題・②配線に関する問題の2科目が試験範囲です。
①写真による鑑別問題
写真による鑑別問題では、絶縁抵抗計やクランプメータ、パイプカッターや圧着ペンチといった、漏電火災報知器の整備・点検に必要な工具などの使い方や名称を問われます。
②配線に関する問題
配線に関する問題では、漏電火災報知器の設置に必要な電気配線の知識を問われます。
また実技試験は筆記試験と違って、”記述式の問題が中心”です。
乙7の科目免除受験について
ネットで多くの方が既に書いているように、乙7試験を受験するほとんどの人が、電気工事士の資格を利用した一部科目免除を利用して受験しています。
私の場合は電気工事士の資格を持っていないため、消防設備士乙6の一部免除を利用して試験に臨みました。
電気工事士の資格を利用した場合は試験のほとんどが免除されますが、消防設備士の免除では、法令共通部分の免除しか受けることができません。
正直、免除を受けても試験が楽になったとは感じませんでした 笑。
他の方のブログなどを読んでいても、電気工事士の資格を利用して試験を受験する場合と、そうでない場合には大きな違いがあるようですね。
消防設備士乙7試験当日の様子

乙7の試験は、危険物や乙6の試験でもお世話になった、幡ヶ谷の中央試験センターに行きました。

受験者の9割が男性で、女性は1割ほどでした。
また、受験者の半分以上は現場の作業員風の方で、25〜40歳くらいの方が多かったです。
乙7試験、受験直後に思ったこと
乙7試験を受験した直後の率直な感想は、「もっと勉強すれば良かった…」でした。
基礎知識は、中学〜高校の理科で習う知識を一夜漬けで思い出す程度で大丈夫です。
しかし漏電火災報知器や機器の構造・工事については、私に馴染みがないためか、聞いたこともないような問題が出題されて全然分かりませんでした。
後悔、後悔、後悔…。
乙7の結果発表は、1ヶ月後
乙7は、試験から約1ヶ月後に合格発表があります。
結果は、ギリギリ不合格。
悔しいです…
乙7受験の感想と今後の対策について
正直”実技試験”と”基礎知識”については、一夜漬けでもなんとかなると感じました。
基礎知識は義務教育で習うレベルで、実技試験は問題集を暗記すれば良いだけなので、2時間も勉強すれば大丈夫です。
しかし、筆記試験の「法令」や「構造」の部分はもう少し勉強する必要があると感じました。
一夜漬けで試験に臨み、時間を無駄にしたことを非常に後悔しています。
正直、舐めてました。
次回受験する際は時間を取って勉強し、万全の状態で乙7合格を目指します!