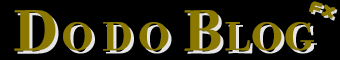こんにちは、資格マニア3年生のどどっちです。
この記事では、消防設備士乙種の資格を取るおすすめの順番や、それぞれの特徴をご紹介しています。
これから消防設備士試験を受けようと考えている方や、消防設備士乙種のフルビットを狙っている方の、参考になれば幸いです。
おすすめの順番①「乙6→乙4→乙7→乙5→乙1→乙3→乙2」

●はじめは、乙6がおすすめ
消火器の整備・点検が可能になる乙6は、需要が多く、一番はじめに取るのがおすすめだと言われています。
また乙6は受験資格がなく、誰でも受けられる点も、おすすめの理由のひとつです。
●王道と言われる順番
「乙6→乙4→乙7→乙1→乙5→乙3→乙2」の順番は、言わずと知れた消防設備士の”王道“と呼ばれる順番です。
実際には”甲種”を挟みながら受験する方が多いので、余裕のある方や、実務上必要な方は”甲種”の資格を早めに取ることをおすすめいたします。
おすすめの順番②「乙6→乙4→乙5→乙7→乙1→乙2→乙3」

●乙4・乙5・乙7はまとめて取る
電気系の知識が必要な乙4・乙5・乙7の3つは、試験範囲が似ているため、なるべくまとめて取ると効率が良いと言われています。
また乙4と電気工事士二種を取った後に乙7を受験すると、試験問題の一部免除がたくさん受けられます。そのため、乙4と電気工事士二種の2つの資格を取った後に、乙7を受験する方も多いです。
●乙1・乙2・乙3はまとめて取る
乙1・乙2・乙3のいずれかの資格を持っていると、残り2つの受験時に、筆記試験の11問が免除されます。
また免除が受けられる類は試験範囲が似ているため、内容が共通している箇所も多く、まとめて受験する事で勉強効率をアップすることができます。
消防設備士乙種の各類を比較してみよう!
①合格率で比較
令和4年度
| 種別 | 合格率 |
|---|---|
| 乙1 | 28.4% |
| 乙2 | 34.3% |
| 乙3 | 28.9% |
| 乙4 | 32.8% |
| 乙5 | 36.6% |
| 乙6 | 38.8% |
| 乙7 | 59.5% |
令和3年度
| 種別 | 合格率 |
|---|---|
| 乙1 | 35.5% |
| 乙2 | 37.0% |
| 乙3 | 33.4% |
| 乙4 | 35.0% |
| 乙5 | 38.5% |
| 乙6 | 39.9% |
| 乙7 | 57.0% |
令和2年度
| 種別 | 合格率 |
|---|---|
| 乙1 | 33.8% |
| 乙2 | 37.5% |
| 乙3 | 34.1% |
| 乙4 | 35.4% |
| 乙5 | 42.9% |
| 乙6 | 42.7% |
| 乙7 | 57.0% |
合格率は、科目免除を利用して問題数を非常に少なくする事が可能な、「乙7」が最も高くなっています。
反対に「乙3」は合格率が最も低い事が多く、取得難易度の高い類だと言えるでしょう。
②対象の設備から検討
| 種別 | 対象設備等 |
|---|---|
| 乙1 | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備 |
| 乙2 | 泡消火設備、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、特定駐車場用泡消火設備 |
| 乙3 | 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備 パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備 |
| 乙4 | 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備 |
| 乙5 | 金属製避難はしご、救助袋、緩降機 |
| 乙6 | 消火器 |
| 乙7 | 漏電火災警報器 |
対象設備の少ない乙6、乙7は、合格率も高い傾向です。
また乙6,乙7は業務の需要も高いため、覚える設備を少なくして、より深い知識を学ぶ仕様になっているようですね。
科目免除を有効活用!
消防設備士の種類を多く取ろうと考えている方には、科目免除を有効活用するのがおすすめです。
取得する順番や、電気工事士などの他の資格を活用することによって、勉強の範囲や時間を大幅に短縮する事が可能です。